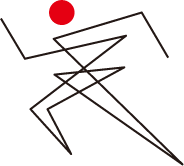第19回Motor Control 研究会
2025年8月20日~22日に、NTT厚木研究開発センターで開催された第19回Motor Control 研究会の参加報告を、3名のボランティアに執筆していただきました。当日の会場の活気と、それぞれにとっての本研究会参加の意義がヒシヒシと伝わるすばらしいレポートです。ぜひご覧ください。
8月20日(大会一日目)
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 彦坂幹斗
例年を上回る酷暑の中、MC19はNTT厚木開発研究センターにて開催されました。100を超える一般演題や厳選されたセレクトトークに加え、東京大学・中澤先生による特別講演、そして多様性に富んだ3つのシンポジウムが行われました。
大会初日、特別講演では、中澤先生がこれまでに取り組まれてきた、スポーツ活動やパラアスリートにみられる興味深い現象を科学的アプローチによって解き明かしてきた数々の研究成果をご紹介くださいました。そのプロセスは、まさに「スポーツニューロサイエンスへの扉」と言えるものであり、基礎研究と応用研究が互いに補完し合い、発展していくことの重要性を改めて感じる機会となりました。神経筋機能や脳構造・機能、ニューロモジュレーションなど多角的な視点から運動制御を探究する姿勢に触れ、知的好奇心を大いに刺激されました。
また、「運動制御の多様性」というテーマは、続く企画シンポジウムにも受け継がれました。櫻田先生、大住先生、古屋先生より、それぞれの立場から実践的な研究の取り組みをご紹介いただき、我々の行動(behavior)が示す問いにどのように向き合うべきか、科学としての理解に加えてトレーニングやリハビリへの応用を意識する視点の重要性を実感しました。 盛夏の熱気に負けないほどの研究熱を感じることができ、学会初日から大いに刺激を受ける最高の一日となりました。
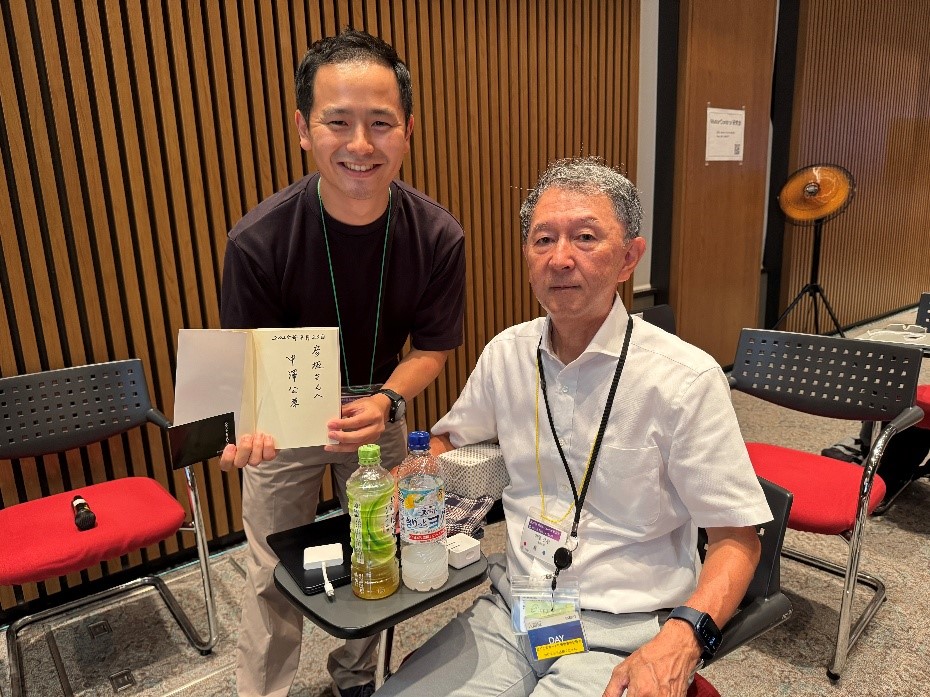
8月21日(大会二日目)
国立研究開発法人情報通信研究機構 牧野勇登
二日目は、「公募シンポジウム」「ポスターセッション」「セレクトトーク」という順番で研究会が取り行われた。戸松先生が主催された公募シンポジウムでは「自己モデルのゆらぎと社会性」がテーマであった。人が他者を含む環境と関わることが運動であり、多くの運動は他者との関わりを伴う。個人の運動実行のメカニズムも重要である一方で、他者とどのように運動を遂行するのか、そしてその意義自体を検討する必要性を痛感するシンポジウムであった。基礎研究をする上で多様な技術の活用をもとに社会にどのような還元ができるか、また運動研究を他分野のコンセプトと融合させる難しさを再考するきっかけとなった。
ポスターセッションでは、学部生からPIまで幅広い世代の研究者が参加し、活発な議論が交わされた。特に、自分の専門分野外からのコメントが新たな視点を与えることを改めて実感した。また、本研究会の特徴として、多数のポスターを知るきっかけとしてフラッシュトークが設けられている。学部生をはじめとする若手研究者が多くの人の前に発表するいい経験であり、また自身とは離れた研究分野のポスターに興味をひくことも多く、魅力的な発表形態であると感じた。
セレクトトークでは5件の発表が行われ、私自身も発表を担当した。運動研究には生理学、計算論、行動実験など多様な切り口が存在する。それぞれのアプローチを深化させることはもちろん、他のアプローチの成果を踏まえつつ研究を展開することが重要であると感じた。さらに、私は修士1年生から本学会に参加しており、これまで数多くの先生方の発表に触れてきた。その中で、研究自体の面白さに加え、わかりやすく伝える発表のあり方を学んできた。研究者にとっては面白い研究を行うことに加え、それを的確かつ魅力的に伝えることも大切な責務であると考えており、今後はその点でも一層精進したい。
最後に、会議運営にボランティアとして関わらせていただいた中で、研究会が多くの方々によって支えられていることを実感するとともに、さまざまな世代間、世代内での交流が促進されるような研究会を運営していく大変さを感じた。特に若い世代の研究者にとって同世代の研究者との交流は、自身が研究を進めていく上での心の支えになると思う。このような貴重な機会をいただけたことに感謝したい。
8月22日(大会三日目)
慶應義塾大学大学院 財津吉輝
最終日となる3日目は、ポスター発表からのスタートでした。前日に発表を終えていた私は聴衆として参加しました。
どのポスターも非常に興味深く、得られた結果から深い考察を展開していたのが印象的でした。脳波や筋電図といった生体信号をはじめ、運動の結果を表す行動計測、さらには瞳孔径、唾液、呼吸といった身体の状態を表す指標など、様々な方法で研究が展開されていたことも印象的でした。MCは今年で自身4回目の参加であり、顔馴染みの参加者も多い中、ポスターでのディスカッションを通じてさらに交友を深めることができました。
昼食を挟んで、最後のプログラムとなる企画シンポジウム2がおこなわれました。テンソル分解を使用した筋電や脳波の解析手法によって、複雑なデータから特徴的な要素を抽出する方法を学ぶことができました。データの解釈をさらに深めることができる画期的な方法であると感じました。
その後の閉会式では、若手奨励賞と人気発表賞の発表がおこなわれました。私の所属する牛山研からは、同期の松本君が若手奨励賞、直属の先輩である杉野さんが人気発表賞を受賞しました。同じラボで切磋琢磨してきた仲間の研究が評価された瞬間に立ち会うことができ、とても幸せでした。
学会期間を通して、互いの研究をリスペクトして讃え合い、より良くするべくディスカッションを重ねることができました。またボランティアしての参加により、同世代との交流を深めることができました。これからの研究活動に必ず役に立つ学びを持ち帰ることができ、非常に充実した時間を過ごすことができました。
 |  |